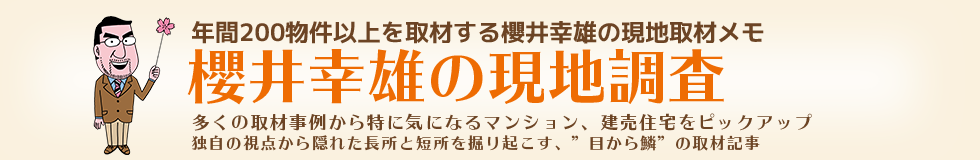
2025年2月、住友不動産様から依頼頂き取材しました。
シティタワー古川橋 (住友不動産、京阪電鉄不動産、ミサワホーム)
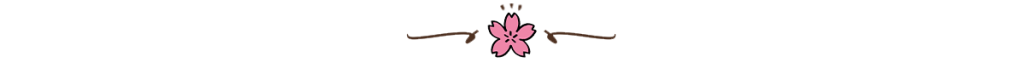
住宅評論家・櫻井幸雄が、分譲中マンション、もしくはこれから販売開始されるマンションをスマホ片手に取材。建設地と最寄り駅、そして販売センターを歩き回り、「どんなマンションなのか」「注目すべきポイントは」を調べる。
今回は、大阪府門真市で2025年春から分譲がはじまる超高層マンション「シティタワー古川橋」をいち早く現地調査した。
昨年から建物の工事が始まり、販売センターでのモデルルーム公開が始まったばかりのマンションである。門真市の古川橋駅に向かい、建設地とモデルルームや展示を詳しくみてまわった。
説明中の動画はコメント入りで、動画中にだけ出している情報もある。ぜひ、音を出して視聴いただきたい。
古川橋駅と建設地の周辺を現地調査する
━━古川橋駅周辺から建設地まで、実際に歩いて立地特性を調査した。
「シティタワー古川橋」の建設地は、大阪府門真市。京阪電鉄京阪本線古川橋駅から徒歩4分という便利な場所だ。古川橋駅から建設地までの距離や建設地周辺の立地特性、将来性の高さを調査した。
調査1 建設地は古川橋駅から徒歩4分の複合開発地内
京阪電鉄京阪本線古川橋駅北口を出ると、駅前ロータリーの向こう側に建設工事のエリアがある。
「シティタワー古川橋」が建設されるのは、この工事エリア内だ。
といっても、工事エリアがすべて「シティタワー古川橋」になるわけではない。同マンションは官民一体で行われる新しい街づくりのなか、公共施設との複合開発で建設されている。

上の写真は、古川橋駅北口から建設地を眺めたところ。正面に3階程度まで骨組みができあがっているのは(仮称)門真市立生涯学習複合施設。2025年度完成予定で、図書館や文化会館の機能を備える計画の建物だ。
超高層タワーマンション「シティタワー古川橋」の建設地は左手奥となり、工事はまだ基礎段階。駅前から見える高さまでは建ち上がってはいない。
駅前から「シティタワー古川橋」の建設地に近い場所に移動すると、驚くことがあった。それは、静かさ。
マンション建設地の近くは、落ち着いて、駅周辺の喧噪から一歩離れた場所だった(下の動画参照)。
駅に近いのに、静か。しかも周囲に高層の建物がないので、眺望が大きく開ける住戸が多くなるはず。つまり、駅徒歩4分で再開発エリア内という利便性の高さに加え、環境のよさも併せ持った立地ということになる。
オフィス用や商業用のビルならば、便利な場所であるだけでよい。しかし、くつろぎが必要な住宅の場合、便利さだけでは不十分。静かさや開放感といった環境のよさも求められる。「シティタワー古川橋」は便利さと環境のよさを併せ持った立地のマンションということになる。この点は高く評価されるべきだろう。
一方で、古川橋駅の南口側には、「そよら古川橋駅前」(イオン古川橋駅前が大規模リニューアルされ、2023年にオープン)をはじめとした商業施設や銀行が集まり、活気がある。
駅に近く、買い物便利な場所で静かな暮らしも実現したい。しかも、これからの発展が見込めて将来の楽しみが広がる場所で……「シティタワー古川橋」は欲張りな希望にもしっかり応える立地のマンションということになる。
参考までに、新しい街づくりで生まれたマンションの一例
今、「シティタワー古川橋」の建設地を見て、完成したときの姿を想像するのはむずかしい。
「新しい街区に素敵なマンションができる」と言われても、今は工事の囲いが見えるだけであるからだ。
そこで、1枚の写真をお見せしたい。
それは、今から10年以上前、2014年の夏に大阪市淀川区に完成したマンションの姿である。

写真のマンションは、阪急神戸線神崎川駅近くで住友不動産が分譲した「シティテラス神崎川」。超高層ではないが、総戸数745戸の大規模マンションだ。
マンションが建設される前、建設地一帯には工場が多く、ごみごみした印象があった。しかし、新しい街づくりが行われ、完成したマンションにより、街のイメージが変わった。
「シティタワー古川橋」の建設地でも、同様の街づくりが行われる。しかも、今回は地上41階建ての超高層……どうしたって、期待が高まってしまうのである。
調査2 よく知らない人のために……古川橋駅、門真市ってどんなところ?
古川橋駅、そして門真市は大阪府の郊外エリアと位置づけられる。大阪中心部までの通勤時間は?街の将来性は?古川橋駅周辺の魅力を探った。
大阪中心の拠点駅まで30分前後。活気を生む街づくりにも注目
京阪電鉄京阪本線古川橋駅は、大阪中心部の淀屋橋駅から直通19分(通勤時20分)。大阪駅へ24分(同25分)、本町駅へ26分(同26分)、新大阪駅へ32分(同33分)など、大阪中心部の拠点駅までいずれも30分前後となる便利な駅だ。
隣駅となる門真市駅では大阪モノレールの延伸計画があり、交通の利便性はさらに向上することが期待されている。
ここで注目したいのは、門真市で複数の新しいまちづくり計画が進んでいることだ。
大阪モノレールの延伸区間につくられる計画の(仮称)松生町駅周辺には「三井ショッピングパーク ららぽーと門真」と「三井アウトレットパーク 大阪門真」が2023年4月オープン(マンション建設地から徒歩19分)、「コストコ門真倉庫店」も2023年8月から開業している(マンション建設地から徒歩21分)。
さらに、古川橋駅と門真市駅の中間地点で門真市役所の建替え計画が進んでおり、2032年に防災機能を備えた公園とともに新しい市庁舎が完成する計画。そして、古川橋駅前で「門真市幸福東土地区画整理事業」が進行。その計画地内に建設される超高層タワーマンションが「シティタワー古川橋」となるわけだ。
「シティタワー古川橋」に住めば、必要な生活利便施設が歩ける範囲にそろう。そして、新しい施設が多い……この最先端エリアに居を構えることができることは、「シティタワー古川橋」の大きな魅力になるだろう。
なぜ、古川橋駅で超高層タワーマンション?その理由を解説
地上60mを超える建物はマンションでもオフィスビルでも「超高層建築物」と分類される。マンションであれば、だいたい地上20階を超えると「超高層」だ。
「シティタワー古川橋」は、地上20階の倍以上=地上41階建ての堂々たる超高層タワーマンションである。
完成すれば、遠くからも目立つ建物となるのは間違いない。そのためか、「なぜ古川橋でタワマン?」の声もある。
タワマンは本来、都心部のもの。門真市の古川橋駅ならば、一戸建てで十分と考えたくなるからだろう。
しかし、駅近くの再開発エリアに一戸建ての住宅地をつくったら、どうなるだろう。
一戸建てであれば、同じ土地面積で建設できる戸数は限られる。駅から徒歩4分で、新しい街づくりが進む場所ならば、「住んでみたい」と思う人は多い。しかし、一戸建てでは、一部の人しか住むことができず、諦める人が多くなる。
また、駅に近い場所で一戸建てを建てると、建物が密集し、住み心地がわるくなりがち。一度火災が起きると延焼しやすいというような問題も懸念される。
その点、超高層タワーマンションであれば、一戸建てよりもはるかに多くの人が居住できる。建物のまわりに広場をつくるなど敷地に余裕をもって建設することで、住戸の開放感が増し、万一、火災が起きても延焼しにくい安全な街づくりが実現する。
つまり、郊外と位置づけられる場所でも、駅に近い再開発エリアは超高層タワーマンションの適正地になるわけだ。
門真市の古川橋駅で超高層タワーマンションが計画されたのは、「便利な場所で、良質な住宅を多くつくりたい」という合理的な理由があるからだ。同じ理由で、今は郊外部でも超高層タワーマンションが増えている。
郊外の超高層タワーマンションは、完成してから注目度がさらに高まる。あんなところに住んでみたいと憧れる人が増えることで資産価値が高く保たれやすいことも付け加えておきたい。
「シティタワー古川橋」は京阪電鉄京阪本線古川橋駅から徒歩4分。「駅近」で、新しい街づくりが行われる街区内に誕生することで、まず注目されるマンションだ。
古川橋駅は、南口側に商業施設が集まり、活気がある。門真市内では新しい街づくりが複数進行し、「ららぽーと」や「コストコ」など大型商業施設もオープン。これからの楽しみが多いエリアとなる。
一方で、マンションの建設地は静かで、環境がよい。周囲に背の高い建物がないので、眺望が開ける住戸が多くなるのも「シティタワー古川橋」の大きな特徴ということになる。
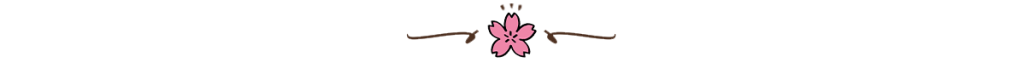
販売センター内の展示やモデルルームで、建物の注目ポイントをプロ目線で解説
━━「シティタワー古川橋」は、地上41階建て、全648戸というスケールの大きさを特徴とする。
地上41階建ては、「超高層」の基準となる「地上20階以上」の倍以上。マンションは総戸数が200戸を超えると「大規模」と呼ばれることが多いのだが、647戸はその3倍以上となる。
門真市では最大規模であり。最高層のマンションとなる。
しかし、それ以外にも建物の特徴は多い。なかでも、私が注目したキーワードは「大林組」「DFS」「ZEH(ゼッチ)」「住みやすさ」「広いバルコニー」だった。以下、建物を現地調査するなかで、キーワードについても説明したい。
調査3 建物の質を見極める
「シティタワー古川橋」は、地上41階建てで全648戸というスケールの大きさに注目が集まりがちだ。では、その建物にはどんな特徴があるのか。販売センターで調べてみるたら、意外な特徴がいくつもあることがわかった。

まず、注目したいのは「大林組」の施工で、最新の制震構造「DFS」であること
「シティタワー古川橋」は、建物の注目点が多いマンションである。
なかでも、建物の質の高さは目を見張るものがある。
たとえば、施工は「大林組」である。

大林組は日本に5社しかないスーパーゼネコンのひとつ(ほかは清水建設、鹿島建設、竹中工務店、大成建設)。大阪で創業し、大阪が“お膝元”となる建設会社である。
そして、「シティタワー古川橋」の建物には、大林組独自の「DFS」制震構造が採用される。これは、建物の芯部分に剛強な壁式構造物を設置。これと建物本体を制震ダンパーでつなぐことで、地震の揺れを低減させる仕組みとなる。地震の揺れを3分の1に軽減させるとともに、風による不快な揺れを生じさせにくいという効果もあるとされる。
DFSは大林組が施工した東京スカイツリーにも採用され、日本免震構造協会賞を受賞している。
すぐれた構造を備えているわけだ。
建設費が大幅に上がっている現在、スーパーゼネコンが施工する超高層タワーマンションに出会うことが少なくなった。スーパーゼネコンに施工を依頼したくてもできないケースが増えているのだ。
しかし、「シティタワー古川橋」は大林組の施工で、DFS制震構造を備えながら、高額住戸をそろえたマンションにならない計画だ。
これは、同マンションの大きな特徴だと考えられる。
「ZEH」(ゼッチ)」マンションであり、そのレベルが高い
「シティタワー古川橋」は、ZEH―M(ゼッチ・マンション)である。近年、ゼッチ・マンションは数が増え、超高層タワーマンションでの採用されるケースも多い。
とはいえ、多くのマンションで見かけるのは「ZEH―M Oriented(オリエンテッド)」の認定。そのなか、「シティタワー古川橋」はオリエンテッドより上位の「ZEH―M Ready(レディ)」を取得予定(2025年2月現在)となっている。

「ZEH―M Ready(レディ)」になると、建物全体の一次エネルギー消費量が50%以上削減され、各住戸の電気代も大幅に削減できることが期待される。光熱費が上がり続けている現在、その恩恵は大きいだろう。
調査4 住戸内をみると、「住みやすさ」のための工夫が多かった
建物の質の高さは共用部だけでなく、専有部(各住戸内)にも感じられる。
販売センターでモデルルームを見学すると、「住みやすさ」のための工夫が多いことに驚いてしまう。
具体的に説明しよう。
モデルルームはスタンダードな広さ
モデルルームは67.65㎡の2LDK+N(納戸)+ウォークインクローゼットの間取り。基本タイプは3LDKの住戸なのだが、2LDKに変更した住戸を見せている。
超高層タワーマンションというと、豪華な住戸をそろえたバブリーな仕様のマンションを思い浮かべる人もいるだろう。しかし、「シティタワー古川橋」はそうではない。
最上階・41階はプレミアムフロアとなり、特殊住戸がそろえられるが、それ以外に特大の住戸はない。普通の人が手の届く価格帯でスタンダードな広さの住戸がそろえられる計画だ。
だから、モデルルームでも約67㎡の住戸を見せている。
3LDKの場合、もう少し広く70㎡の広さが欲しいという人もいるだろう。しかし、最新のマンションは室内廊下を短くし、室内への廊下の食い込みを減らすなどの工夫を凝らし、約67㎡でも実質70㎡の暮らしができるようになっている。
バブリーな住戸ではなく、普通の住戸でも「住みやすさ」を追求しているわけだ。工夫の中身をモデルルームで撮影してきた。
まず、玄関前のアルコーブに注目
モデルルームに入る前に注目したい部分がある。それは、玄関前にアルコーブ(くぼみ)が設けられていることだ。
「シティタワー古川橋」はホテルのような内廊下方式を採用しているのだが、各住戸の玄関前に深いアルコーブ(くぼみのように設けた玄関前スペース)を設けている。内廊下に面して玄関が並ぶわけではない。これ、意外に採用例が少ない工夫だ。
室内の工夫を紹介したい
室内廊下は極めて短くして室内の有効面積を拡大。その分、居室や収納をゆったりと……賢い工夫である。
玄関の収納部分には、取っ手が邪魔にならないようにする工夫など、「住みやすさ」を実現する細やかな心配りがあった。
さらに、「住みやすさ」を追求する工夫を紹介
「シティタワー古川橋」の住戸プランは、超高層マンションにありがちな住戸内への柱の食い込みが極めて少ない。プランはすべてきれいな正形のプランで家具の配置がしやすく、住みやすい間取りと評価される。
天井が高く、下がり天井が少ないのも「シティタワー古川橋」の建物特性だ。リビング部分での天井高は2m60㎝に。一般的なマンションは天井高2m40㎝程度なので、モデルルームに入ると、大きな開放感を感じる。
キッチン設備は充実し、豪華さもある。
天板は天然の御影石で、ディスポーザー(生ゴミ粉砕処理機)、食器洗い乾燥機も実装している。以上の設備で、自慢したくなるようなキッチンが実現する。
リビング側から丸見えになるオープンタイプのキッチンに対し、「こうなっていればいいよね」という設備が網羅されているわけだ。
さらに、キッチンにはひとクラス上の設備も入っている。それは、引き出しがソフトクロージングになっていること。引き出しがゆっくり閉まるようになっているわけだ。また、同時吸排型レンジフードを採用していることも注目したい。
排気をするだけでなく、同時に吸気も行うため、換気扇を作動させたとき、サッシュからの風切り音が軽減される。さらに、玄関ドアを開けるときに妙に重いと感じることがない……そんなプロ好みの特徴もあるのだ。
最後のキーワード「広いバルコニー」に注目する理由
「シティタワー古川橋」のバルコニーは広い。奥行2mとたっぷりした広さで、モデルルームでは椅子が置かれてた。
超高層マンションのバルコニーに家具を置くの?と疑問を抱く人もいるだろう。
もちろん、強い風が吹く日に家具を置くことはできない。室内にしまうことが求められる……しかし、風がなく、穏やかな昼下がり、超高層タワーマンションでは、バルコニーに椅子とテーブルを持ち出す人が多いのだ。
飲み物片手にゆっくりと時を過ごす。そのような過ごし方をする人が多いので、最新の超高層タワーマンションで広いバルコニーを採用するケースが増えている。
特に、郊外の超高層タワーマンションで、その傾向が強い。都心部の超高層タワーマンションでは、室内から夜景を眺める人が多い。それに対し、郊外の超高層タワーマンションでは、昼間や夕方、バルコニーで風を感じながら空や台地を眺める人が多いからだと、私は考えている。
「シティタワー古川橋」では、目の前に高層の建物がなく、眺望の開けた住戸が多くなる。周囲からの人目を気にせず、バルコニーライフを楽しむこともできる。だから、広いバルコニーで過ごす時間が多くなりそう……それも「シティタワー古川橋」の特徴といえるだろう。
「シティタワー古川橋」は、建物の特徴が多いマンションである。
スーパーゼネコンの大林組の施工で、スカイツリーにも採用されている最新の制震構造「DFS」が用いられる。
「ZEH―M Ready(レディ)」の認定を受け、省エネ性能が高いことも建物の特徴となる。
最上階の一部住戸を除き、標準的な広さで、住みやすさを重視した住戸プランニングが行われている。
具体的には、室内の有効面積を拡大し、天井が高く、下がり天井が少ない。ディスポーザーや食器洗い乾燥機、同時吸排型レンジフードなど生活の質を高める設備機器を採用している。
バルコニーを広くするなど、郊外立地の超高層タワーマンションに求められるつくりになっている点にも注目したい
「シティタワー古川橋」は、挑戦的なマンションでもある。
これまで、超高層マンションがなかった郊外に、地上41階建て、全648戸というスケールの大きなマンションをつくろうとするのだから。
前例のない物件であるため、「なぜ、門真市に?」「なぜ、タワマン?」ととまどう人もいるはずだ。
しかし、他にない特徴を備えたマンションは、完成した後、長く注目を集め続ける。「住んでみたい」と憧れる人も出てくる。それが、資産価値を維持する力となる。
なお、「シティタワー古川橋」は取材を進める段階で、第1期で販売される住戸の価格が見えてきた。
いろいろな情報を基に推測すると、坪単価(3.3㎡あたりの分譲価格)は400万円を切り、300万円台中盤程度から400万円弱となりそうだ。
具体的な住戸価格に置き換えると、3LDKは8000万円未満に
建設費が上昇する現在、大阪府で300万円台中盤程度の価格を実現しているタワーマンションは定期借地権方式になってしまうのが実情だ。
定期借地権マンションだと、最終的に資産として残らないことを残念に思う人もいる。その点、所有権のマンションならば、子供たちも安心だ。
今、タワーマンションは建設費だけでも坪単価300万円に達するようになってしまった。建設費だけで坪あたり300万円であれば、分譲価格を坪あたり400万円で納めるのはこの先、どんどんむずかしくなるだろう。
「シティタワー古川橋」の価格は予測どおり、坪あたり400万円を切ることを願いたいところである。
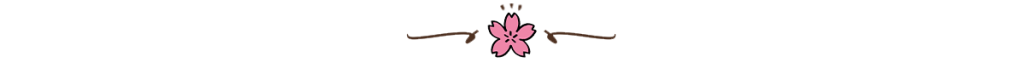
◆「シティタワー古川橋」公式サイトはこちら
記事や動画内の気になる用語をプロの視点で解説
◆櫻井幸雄の用語解説「40年の取材でわかった住宅設備のリアル」

