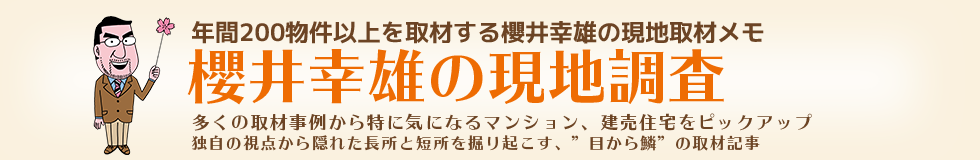
2025年10月、住友不動産様から依頼頂き取材しました。
シティタワー古川橋 (住友不動産、京阪電鉄不動産、ミサワホーム)
2025年10月公開・特別編
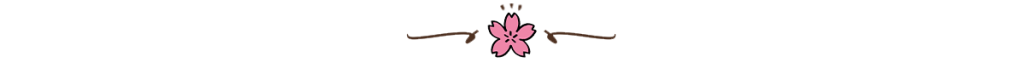
住宅評論家・櫻井幸雄が、分譲中マンション、もしくはこれから販売開始されるマンションをスマホ片手に取材。建設地と最寄り駅、そして販売センターを歩き回り、「どんなマンションなのか」「注目すべきポイントは」を調べる。
今回は、大阪府門真市で2025年7月末から分譲がはじまった超高層マンション「シティタワー古川橋」の2回目。
2025年2月に現地調査を行った後、約8カ月経ってもう一度建設地周辺を取材した。それは、工事が進んだ現地にどのような変化が生じているのか、現地で確認して解説したかったから。
さらに、約8カ月の間の市況の変化も解説したかった。
2025年に入り、近畿圏の不動産市況にはいくつかの変化がみられた。この変化で、同マンションの評価がどのように変わってきたのか。現地の取材を通した感想を含め、解説する。
基本的な調査は2025年2月の取材で行っている。
そのコンテンツを残しながら、今回は現地での解説を中心にした特別編として公開する。
2025年2月の現地調査も参照しながら、閲覧いただければ幸いだ。
なお、説明中の動画はコメント入りで、動画中にだけ出している情報もある。ぜひ、音を出して視聴いただきたい。
古川橋駅と建設地の周辺を調査・解説
━━「シティタワー古川橋」の建設地は、大阪府門真市。京阪電鉄京阪本線古川橋駅から徒歩4分という便利な場所だ。古川橋駅の前に立つと、30階以上建ち上がった建物の様子が目に飛び込んでくる。
「駅のすぐ近くで、ひときわ背の高いマンション」となり、目立つこと間違いなし。建設地周辺の立地特性、将来性の高さを改めて評価した。
現地で解説1 古川橋駅から徒歩4分、新しい街区の様子が見えてきた
京阪電鉄京阪本線古川橋駅北口を出ると、駅前ロータリーの向こう側にみえる工事エリア。
そのなか、建設中の「シティタワー古川橋」がそびえ立っていた。
今年2月の時点では、大型クレーン2基の姿はみえたが、建物は基礎工事の段階で、全体像はわからなかった。それから8カ月経った10月はじめ、巨大な建物の様子が分かる。

建設中の建物には「15F」「20F」といった表示があり、最も高い場所にある表示が「25F」と読めた。つまり、30階以上まで骨格ができていることが分かる。
「シティタワー古川橋」は、完成すれば地上41階建てとなる。現在の状況からさらに10階程度高くなるわけだ。
地上20階以上が「超高層」と呼ばれる目安。その倍以上の高さとなるため、周囲を圧倒する建物になることは間違いない。
ちなみに、写真の工事エリアすべてが「シティタワー古川橋」になるわけではない。同マンションは官民一体で行われる新しい街づくりのなか、公共施設との複合開発で建設されている。超高層マンションの右手前で工事が進んでいるのは(仮称)門真市立生涯学習複合施設。2026年春開館予定で、図書館や文化会館の機能を備える計画の建物だ。
「シティタワー古川橋」の建物だけでなく、広い範囲で新しい街区ができる。そして、エリアに活気が出る……その様子が今から想像できる光景である。
「シティタワー古川橋」の注目すべき立地特性
「シティタワー古川橋」の建設地には、注目すべき特性がいくつもある。
まず、古川橋駅は大阪中心部の拠点駅たとえば、淀屋橋駅や大阪駅、本町駅、難波駅などから30分程度の所要時間で、利便性が高い。
同時に「シティタワー古川橋」が所在する大阪府門真市では複数の新しいまちづくり計画が進んでいる。
大阪中心部へのアクセスがよく、将来の楽しみも多い場所となるわけだ。
さらに、建設地に近づくと落ち着いていて、駅周辺の喧噪から一歩離れていることを感じた。
一方で、「なぜ、郊外エリアで超高層タワーマンションを建てるのか。一戸建てでよいのでは」という声があるのも、事実だ。
なぜ、郊外の古川橋駅で、駅に近い超高層タワーマンションを建設するのか。それについては、前回の現地調査で解説を行った。
その解説動画だけ再度、ここでも紹介したい。
要点をまとめると、次のようになる。
・門真市の古川橋駅ならば、一戸建てで十分と考えられがち。しかし、駅近くの再開発エリアに一戸建ての住宅地をつくったら、建設できる戸数は限られる
・また、駅に近い場所で一戸建てを建てると、建物が密集し、住み心地がわるくなりがち。一度火災が起きると延焼しやすいというような問題も懸念される。
・その点、超高層タワーマンションであれば、一戸建てよりもはるかに多くの人が居住できる。建物のまわりに広場をつくるなど敷地に余裕をもって建設することで、住戸の開放感が増し、万一、火災が起きても延焼しにくい安全な街づくりが実現する。
・つまり、郊外と位置づけられる場所でも、駅に近い再開発エリアは超高層タワーマンションの適正地になるわけだ。
現地で解説2 近畿圏で起きている不動産市況の変化とは
今回の調査報告では、マンションの特徴だけでなく、今、近畿圏に生じている不動産市境の変化についても解説したい。
というのも、私は数多い取材を通し、郊外で駅に近い場所で開発されるマンションの注目度が高まっていることを感じているからだ。
自ら住む目的で、新築分譲マンションを探している人たちは、準都心や近郊外と位置づけられる場所で、なるべく駅に近い物件を熱心に探すようになった。それは、大阪を中心とする近畿圏でも、東京を中心とする首都圏でも感じられる傾向である。
なぜ、そのような傾向が生まれているのか。
私の考えを動画で解説しよう。
動画の要点をまとめると、次のようになる。
・今、近畿圏の新築分譲マンション価格は大きく上がり、不動産経済研究所の発表によると、2025年8月の近畿圏全体の平均価格は5440万円になった。
・大阪中心地は3LDKが1億円に届こうとしている。
・普通のサラリーマンが購入できる3LDKは6000万円台まで。できれば5000万円台までで買いたいと願っている。
・その価格帯で購入できる新築分譲マンションが、郊外部でまだなんとか残っている。
・一方、夫婦共働き世帯は、できるだけ便利な郊外で、駅に近く、買い物便利なマンションが好まれる。
・そのようなマンションであれば、資産性も期待できる。
・「シティタワー古川橋」は、多くの条件を満たしたマンションと評価できる。
「シティタワー古川橋」は京阪電鉄京阪本線古川橋駅から徒歩4分。「駅近」で、新しい街づくりが行われる街区内に誕生することで注目されるマンションだ。
その建物が30階程度までできあがり、目立つ建物になる様子がみえてきた。
古川橋駅は、南口側に商業施設が集まり、活気がある。門真市内では新しい街づくりが複数進行し、「ららぽーと」や「コストコ」など大型商業施設もオープン。これからの楽しみが多いエリアとなる。
一方で、マンションの建設地は静かで、環境がよい。周囲に背の高い建物がないので、眺望が開ける住戸が多くなるのも「シティタワー古川橋」の大きな特徴ということになる。
近畿圏で新築マンション価格が上がる中、門真市の古川橋駅で超高層タワーマンションが計画されたのは、「便利な場所で、良質な住宅を多くつくりたい」という合理的な理由があるからだ。同じ理由で、今は郊外部でも超高層タワーマンションが増えおり、今後はさらに増えることが予想されている。
それに伴い、価格も上がってくる懸念がある。「人気ジャンルの物
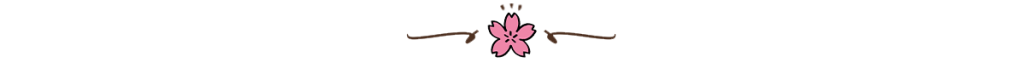
価格上昇が顕著な今、改めて建物の特性を見極める
━━シティタワー古川橋」には「建物の質が高い」という特徴があり、マンション価格上昇の今、価格と質のバランスに注目する人が増加している。
「シティタワー古川橋」は門真市では最大規模であり、最高層のマンションとなる。
しかし、それ以外にも建物の特徴は多い。前回調査で私が注目したのは「大林組」「DFS」「ZEH」「住みやすさ」「広いバルコニー」だった。
以上は、新築マンション価格が上昇している今、ますます実現しにくいものとなっている。後半では、不動産市況の変化やモデルルームで注目したいポイント、そして、郊外新築分譲マンションに生じている最新の現象について解説したい。
現地で解説3 建物の質が高いと感じるポイントは
「シティタワー古川橋」の建物にはどんな特徴があるのか。全国的に地価が上昇し、近畿圏、首都圏では新築分譲マンション価格の上昇が顕著な今、同マンションの注目すべき建物特性について改めて考えてみた。

最大の特徴は「大林組」の施工で、最新の工夫、贅沢な仕様を多く採用していること
「シティタワー古川橋」は、建物の注目点が多いマンションである。それについては、前回の現地調査でも詳しく説明している。
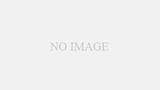
その要点をまとめると、以下のようになる。
・施工はスーパーゼネコンの「大林組」。そして、大林組独自の「DFS」制震構造が採用される。この構造は大林組が施工した東京スカイツリーにも採用され、日本免震構造協会賞を受賞したものだ。
・「ZEH」(ゼッチ)」マンションであり、一般的な「ZEH―Mオリエンテッド」より上位の「ZEH―Mレディ」を取得予定となっている。
・建物内では、ホテルのような内廊下方式を採用し、各住戸の玄関前に深いアルコーブ(くぼみのように設けた玄関前スペース)を設けている。これ、意外に採用例が少ない。
・住戸内は天井が高く、下がり天井が少ない。リビング部分での天井高は2m60㎝(一般的なマンションは天井高2m40㎝程度)となっている。
・キッチン設備は充実し、豪華さもある。
・バルコニーが広く、奥行1.8mとたっぷりした広さとなる。
・建設費が上昇している現在、そのような建物の質の高さに注目する購入検討者は多い。
なかでも特に注目したいのは、キッチンの豪華さだ。それは、住み始めてからの満足度を大きく高めてくれるはずだ。
理由を改めて解説したい。
大阪中心地の一部高額マンションにみられるような「華美な装飾」を施すのではなく、実質的に生活を快適にする設備仕様を重点的に採用している。
それも、「シティタワー古川橋」の建物特性だと考えられる。
現地で解説4 郊外の駅近マンションにみられる最新の傾向とは
現地での解説の最後に、郊外駅近マンションに生じている、最新傾向について説明したい。
それは、シニアの購入者が増えているということ。この1、2年、50代以上の購入者が目に見えて増加している。それは近畿圏でも首都圏でも見られる現象だ。
購入しているシニアの多くは買替え組。それまで住んでいたマンション、一戸建てを売却して郊外マンションの3LDKや2LDKを購入する人たちである。
なぜ、そんな状況が生まれているのか……まず、マンションからマンションへの買い替えが行われる経緯を説明したい。
要約すると、大阪中心部のマンション価格が上がり、都心マンションに住んでいた人は自宅マンションが思いのほか高く売れるという事態が生じた。都心マンションを高値で売却した後、次の住まいとして、郊外で駅に近いマンションを購入する動きが出ているのだ。
その場合、ローンを組まず、キャッシュで購入。ローン返済のない老後生活を確保する。新たに購入する郊外・駅近マンションは、車なしでも便利に生活できるし、将来値上がりする可能性も高いと考えている。
賢い買い替え術として、郊外・駅近マンションを選択しているわけだ。
次に、一戸建てからマンションへの買い替えを行うシニアの動きについて。
要約すると、今、郊外の一戸建ては中古で売りにくくなっている。この先はさらに値下がりする可能性が高い。そして、子供たちは相続したくないという。
だったら、売れる内に売却し、便利に生活できる郊外・駅近マンションに買い替えようとしている。
この場合も、「郊外の駅近マンションならば、この先値上がりする可能性が高い」という読みが買い替え決断を後押しする。
以上の考え方で、シニアが郊外・駅近マンションを買う動きが広まっているわけだ。
「シティタワー古川橋」の場合、これまで購入を決めた人のおおよそ4割が50歳以上だという。
多くのシニアがこのマンションに目を付けている。その理由として、「シティタワー古川橋」の販売価格も大きいだろう。
今回の取材を行った2025年10月時点で同マンションの価格帯は「68.03㎡の3LDKが5300万円台から」となっていた。
この価格を頃合いと考えるのはシニア以外でも、少なくないはずだ。
不動産価格の上昇期は「まだ上がっていない」場所でつくりのよい新築物件を狙う……それが、マイホーム購入の鉄則であるからだ。
最後に若い購入層向けのアドバイスをお話ししたい。
若い層へのアドバイスでポイントとなるのは、「シニアになったら、郊外・駅近マンションを選択する人が多い」ということ。最終的に、郊外・駅近マンションが好ましいことになるのなら、若いとき、最初に買うマンションも郊外・駅近でよいという考え方もできる。そのほうがロスが少ないからだである。
「シティタワー古川橋」は、建物の特徴が多いマンションである。
スーパーゼネコンの大林組の施工で、スカイツリーにも採用されている最新の制震構造「DFS」が用いられる。
「ZEH―Mレディ」の認定を受け、省エネ性能が高いことも建物の特徴となる。
室内の有効面積を拡大し、天井が高く、下がり天井が少ない。ディスポーザーや食器洗い乾燥機など生活の質を高める設備機器を採用している。
バルコニーを広くするなど、住み心地を高める工夫が多い点にも注目したい。
その販売価格は2025年10月時点で、68.03㎡の3LDKが5300万円台から。
このつくりで、この価格ならば購入したいと考えるシニアが多い。
このことは、若い世代も知っておく必要がある。シニアになってか
郊外の超高層タワーマンションは、完成してから注目度がさらに高
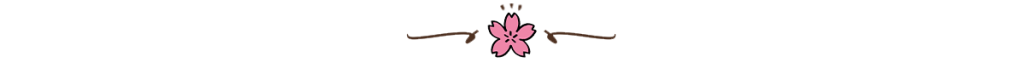
◆「シティタワー古川橋」公式サイトはこちら
記事や動画内の気になる用語をプロの視点で解説
◆櫻井幸雄の用語解説「40年の取材でわかった住宅設備のリアル」

